舞台芸術の世界 -ディアギレフのロシアバレエと舞台デザイン- A World of Stage: Russian Designs for Theater, Opera, and Dance
20世紀前半のロシアは、舞台芸術の世界において新時代を切りひらき、世界中のエンターテインメントシーンに大きな影響を及ぼしました。本展覧会では、ニューヨーク、パリ、ロンドン、サンクトペテルブルク、そして日本国内から集められたデザイン画、当時の舞台衣装、ポスター、上演プログラム、再演映像など約190点の作品資料により、当時のロシア舞台芸術における多様なデザインの動向を紹介します。

レオン・バクスト 《男性の衣装(バレエ『シェエラザード』より)》1910年 サンクトペテルブルク国立演劇音楽博物館蔵 ©Texts,photos, The State Museum of Theatre and Music, St.Petersburg, 2007
開催概要
会期
2007年9月29日 (土) – 10月28日 (日)
※会期中無休
開館時間
9:30 – 17:00 (入館は16:30まで)
※9月29日、30日は9:00 – 18:00 (入館は17:30まで)
観覧料
舞台展+アレコ
一般 800円 (700円)
高大生 560円 (460円)
小中生 320円 (220円)
舞台展+常設展
一般 1,200円 (1,100円)
高大生 800円 (700円)
小中生 400円 (300円)
※( )内は前売券および20名以上の団体料金
※心身に障がいのある方と付添者1名は無料 (入館の際に証明できるものをご呈示ください)
主催
舞台芸術の世界展実行委員会 (青森県立美術館、青森放送、陸奥新報社)
後援
ロシア連邦大使館
協賛
イマジン株式会社
協力
ANA、ルフトハンザ ドイツ航空、ルフトハンザ カーゴAG
企画協力
アートインプレッション
お問合せ
舞台芸術の世界展実行委員会 (青森県立美術館内)
住所 〒038-0021 青森市安田字近野185
Tel 017-783-5241 / 017-783-3000
Fax 017-783-5244
チケット販売
前売り券発売所
サークルKサンクス(サークルK:青森、秋田、岩手県内の各店舗 サンクス:東北各県、北海道央、道南地区の各店舗)、サンロード青森、イトーヨーカドー青森店・弘前店、成田本店しんまち店Pax、さくら野百貨店青森店・弘前店・八戸店、中合三春屋店、県内JTB及びJTBトラベランド、県内日本旅行、県内近畿日本ツーリスト、県庁生協・青森県民生協、弘大生協、青森市文化会館、青森県立美術館ミュージアムショップ
展示内容
ロシア舞台芸術の夜明け
19世紀後半から20世紀初頭にかけて、ロシアは大きな変動の時代を迎えていました。資本主義経済への移行に伴い、商売により財をなした実業家など新たな富裕層が貴族にかわり台頭するようになると、彼らは芸術の分野においても時代の牽引力となっていきます。
その結果、西欧の新しい芸術動向に対して積極的に目が向けられるようになり、さらにはロシア芸術の独自性が社会的、民俗的観点から模索されるようになります。
1885年、モスクワの鉄道王サッヴァ・マーモントフは私的なオペラハウスをモスクワ近郊に建て、作品の上演をはじめます。そこで彼は舞台美術専門の職人ではなくロシアの代表的な画家達を起用、芸術家が舞台芸術と深く関わることになりました。ロシア舞台芸術の新時代が到来したのです。
伝説のバレエ団「バレエ・リュス」の驚くべき世界
このような状況の中、20世紀初頭のロシアに登場したのが興行主セルジュ・ディアギレフでした。優れた芸術批評家でもあったディアギレフはバレエこそが舞踊、美術、音楽を統合させた「総合芸術」であるという信念のもと、ロシアの舞踊家、画家、音楽家からなるバレエ・リュス(ロシア・バレエ団)を組織し、1909年パリにデビューします。野性的なリズムを際立たせ、不協和音を多用した音楽を作曲したイーゴリ・ストラヴィンスキー、金、赤、緑、紫など濃厚な色彩によって官能的かつ非西欧的な美学に彩られた舞台美術をデザインしたレオン・バクスト、そして圧倒的なテクニックとともに性的な魅力をたたえた舞踊を披露した天才ダンサー、ワツラフ・ニジンスキー・・・その他ディアギレフの眼にかなった芸術家達が一体となって創り出したバレエという「総合芸術」の世界は、当時の人々に大きな衝撃を与え、歓声と怒号を浴びながら瞬く間にヨーロッパを席捲していきました。

レオン・バクスト
《ワツラフ・ニジンスキーのための衣装デザイン(上演されなかったバレエ『ペリ』より)》1911年
Coll. Professor Stavrovski, New York
芸術の実験場としての舞台芸術
しかし、当時の舞台芸術における画期的な動きは、ディアギレフのバレエ・リュスに限った現象ではありませんでした。ロシア国内では1917年のロシア革命の前後に展開された総合的な芸術運動《ロシア・アヴァンギャルド》を背景に、舞台においても実験的な試みが次々におこなわれます。
初期ロシア・アヴァンギャルドを代表する舞台の一つに、全てが機械化された未来世界を描いた“初の未来主義オペラ”『太陽の征服』(1913年)があります。「ZAUM」(ザーウミ/超意味言語)と呼ばれる、語呂合わせや音の自由な連なりを重視した新言語によって書かれたテキスト、俳優の動きや台詞に合わせて鳴り響く不協和音、そしてカシミール・マレーヴィチによる幾何学的で動的なデザインの舞台装置やコスチュームをとりいれたこの舞台は、それまでの平面的な舞台背景を変革し、舞台装置と俳優との律動的で有機的な結びつきを生みだしました。そして、これが1920年代ロシア舞台芸術におけるデザインの大勢となっていったのです。

ラザリ・ヒデーケリ
《登場人物スケッチ(オペラ『太陽の征服』より)》1920年
Coll. The Khidekel Family, New York
*『太陽の征服』再演(1920年)のために制作
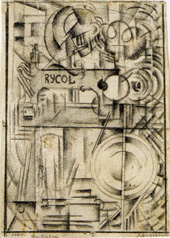
ラザリ・ヒデーケリ
《舞台デザイン(オペラ『太陽の征服』より)》1919年
Coll. The Khidekel Family
New York
*『太陽の征服』再演(1920年)のために制作
大衆エンターテインメントとキャバレー文化
一方、ロシアの舞台芸術家達は演劇やオペラ、バレエといった専門的な舞台芸術に飽きたらず、豊かな大衆階層に向けた活動をキャバレー(*舞台付きの小さなカフェやレストラン)と呼ばれる小さな舞台空間で提供するようになります。ここではサーカスや見世物的なパフォーマンス、歌手やダンサーによる短いショー、笑劇などが繰り広げられ、広く人気を博しましたが、こうした小劇場は同時に、大劇場のような観客動員の圧力にさらされることのない自由な空間として、前衛的な芸術表現が試みられ、また社会問題をテーマにした風刺的作品が上演されるなど先進的な実験工房としての役割も備えていました。1908年にニキータ・バリーエフが開いたキャバレー〈こうもり座〉は当時特に人気の高かったキャバレーの一つで、ロシアの伝説的なオペラ歌手ヒョードル・シャリアピンや20世紀最大の演劇人とも称されるフセヴォロド・メイエルホリドなどの著名人も、このキャバレーの舞台に立っていました。

ニキータ・バリーエフ
《こうもり座のための楽譜》1921年
表紙:S・スデイキン
Coll. Professor Stavrovski, New York
亡命ロシア舞台人達の活躍
20世紀初頭のロシアに立て続けに起こった第一次世界大戦と革命は、国内の政情不安を招き、深刻な食糧不足を引き起こしました。そして、1922年にソビエト連邦が成立すると、その指導者達はまもなく芸術の自由な表現を規制し、革新的な表現に挑む芸術家達を「頽廃」という名の下に弾圧し始めました。このような状況の中、ロシアの芸術家の多くは自由な表現の場を求めて祖国ロシアを離れ、西ヨーロッパ諸国やアメリカへ渡ります。こうして活気溢れるロシア舞台芸術の世界はその後、世界各国の劇場へとその活躍の場を移し、各国の舞台芸術に大きな影響を与えることとなりました。

アレクサンドラ・エクステル
《舞台デザイン(バレエ『ドン・ファン』より)》
ヴィクトリア・アンド・アルバート美術館蔵
*本作品は1927年ケルン歌劇場上演のために制作
シャガールと舞台芸術
青森県立美術館はロシア出身の画家、マルク・シャガールが手がけたバレエ『アレコ』(*)の舞台背景画3点を所蔵し、常設展示しています。そのシャガールは、自伝『わが回想』の中で次のように振り返っています。「劇場のために働くこと、これは昔からの私の夢だった」。
1908年、20歳の若きシャガールはサンクトペテルブルクにあったスヴァンセヴァ美術学校に入学しますが、ここで師事したのが後にバレエ・リュスの舞台デザイナーとして活躍することになる画家レオン・バクストでした。この美術学校には当時、すでにダンサーとしての頭角をあらわしていた若き日のワツラフ・ニジンスキーも学んでおり、この頃から舞台芸術の世界はシャガールにとって身近なものとなっていました。まもなくしてパリに出たシャガールは、バレエ・リュスの成功を目の当たりにします。その後、1914年に一時ロシアに帰国、第一次世界大戦と、それに続くロシア革命を経験した後、革命政府により故郷ヴィテブスクの芸術人民委員に任命され、ヴィテブスクにつくられたテレフサート(革命的諷刺劇場)で数年間にわたって舞台美術を担当します。また、1920年、モスクワに転居した際にはユダヤ劇場のための舞台壁画を制作、そこで上演された作品の舞台美術等も手がけました。その後、シャガールは1922年に再び祖国ロシアを離れてパリへ向かいますが、途中、一時立ち寄ったベルリンでは、当地で大変な人気を博していたロシア・キャバレー〈青い鳥〉の舞台装置を描くなどして生活を支えました。また、第二次大戦中は、ナチスから逃れてアメリカ亡命中の1942年にバレエ『アレコ』の、1945年にバレエ『火の鳥』の舞台美術を手がけ、戦後はバレエ『ダフニスとクロエ』やオペラ『魔笛』の舞台美術を手がけました。このように、シャガールの画家としての人生は常に舞台芸術との関わりの中で存在していたといえるのです。
*バレエ『アレコ』は、バレエ・シアター(現:アメリカン・バレエ・シアター)により1942年に初演された全4幕のバレエ。プーシキンの叙事詩『ジプシー』を原作としたストーリーで、音楽にはチャイコフスキーの「イ短調ピアノ三重奏曲」(編曲)が用いられました。振付をバレエ・リュスでも活躍したロシア人ダンサー、レオニード・マシーンが、舞台美術をシャガールが担当する等ロシア的色彩に彩られたこのバレエは、バレエ・リュスの精神を新大陸において甦らせようとした試みでもありました。

レオン・バクスト
《ミハイル・フォーキンのための「アムーン」の衣装(バレエ『エジプトの夜』より)》
Coll. Professor Stavrovski, New York
©Texts,photos, The State Museum of Theatre and Music, St.Petersburg, 2007
*本衣装は1908年サンクトペテルブルク・マリインスキー劇場で初演された『エジプトの夜』のために制作。1909年ディアギレフのバレエ・リュスによるパリ・シャトレ劇場上演でも使用

