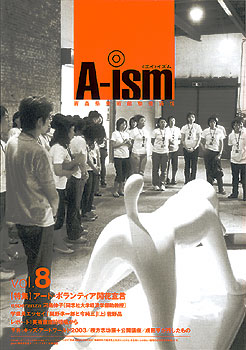
A-ism vol.8
アート・ボランティア開花宣言
美術館にとってボランティアは「内部に組織された存在」から、「外部にあって美術館を支援する組織」へとシフトしています。そしていま、ボランティア・スタッフによって、公立美術館の企画展を凌駕する大型展覧会を実施し成功をおさめるなど、画期的な状況が生まれつつあります。青森県内のこうした動向は、全国的に大きな注目を集めると同時に、美術館活動そのものにも大きな影響を与え、変化をもたらすことでしょう。
ボランティアに開かれた美術館をめざして
黒岩恭介(青森県美術館整備推進監)
今海外国内を問わず、美術館を舞台に様々なボランティア活動が展開されている。多くは展示作品の解説であったり、美術館の収集する一次資料、二次資料の分類整理であったり、あるいは受付や監視を担当するボランティアであったりする。 展示室の入り口で、入場者を待ち構えていて、鑑賞者の一人一人に解説は要りませんかと声をかけているボランティアを目撃した経験をもつ人は結構多いのではないだろうか。
そういった美術館におけるボランティア活動は、美術館サイドから見ると、十分な予算と人員を持つことの困難な状況にあっては、大変有り難く、一定の美術館サービスを維持するためには、いまや必要不可欠な要素であるように見える。しかし一方で、本来なら美術館の専門スタッフがやるべき仕事を、ボランティアに頼っているのではないかという批判にもさらされがちである。
また鑑賞者側から見ると、そのような解説ボランティアとのやり取りの中で、もしそのボランティアに、十分な美術史的な知識と素養そして作品に対する熱意みたいなものが感じられる場合は、眼からウロコが落ちるような、啓発的な経験が可能となり、解説を頼んでよかったという大変ほほえましい状況が生まれる。しかしそうでない場合、中途半端な知識で、マナーを欠いたバスガイドのような応対をされると、かえって欲求不満状態を出来させないともかぎらない。解説をはじめ監視や受付といった鑑賞者と直接対峙する場面で活動するボランティアの難しさはここにある。
最後に最も重要な視点であるボランティアサイドから見てみよう。ボランティア活動を志す側にとって、美術館は実に魅力的なステージではないだろうか。文化を通して社会にコミットできるという状況は他の分野にはみられない動機付けであると思うし、作品やアーティストと直に接触することができるという特権も、実に得がたい。美術館ボランティアには、ただ、それぞれの活動分野で、固有の知識と能力が要求されることは言っておかねばならない。解説ボランティアであれば、日々美術(史)の勉強は怠れないし、美術作品を見たいという好奇心も旺盛でなければならない。人前に出るよりも資料の整理など、美術館を裏方で支える方を志向するボランティアには、根気強い、持続的な整理能力と責任感がいる。またアーティストのお世話などをしたいというアテンド・ボランティアには、人柄の温かさややさしさ、気配りの能力が必要となる。その他、ボランティアには、たとえば、地域住民に対するマーケティングや情報発信など、県民と美術館とをつなぐパイプ役となるといったことも考えられるし、場合によっては、企画アイデアの提供といった美術館の中枢に関与することも可能かもしれない。
いずれにせよ、青森県の美術館は、そのような様々な才能・能力を美術館の運動の中で発揮してみたいというボランティアに対して、常に開かれている施設でありたいと思う。青森県の美術館は開放系の運動体を目指しているのであるから。
変わる〈美術館ボランティア〉 −「奈良美智展」以前・以後−
高橋しげみ(学芸員)
昨年の夏に弘前市の吉井酒造煉瓦倉庫を舞台に開催された「奈良美智展弘前」は五百人を超えるボランティアの活躍で大きな話題をよんだ。この展覧会は運営それ自体、さまざまな職種のボランティアで構成された実行委員会によって行われていた。メンバーには、展覧会の仕掛け人だった当課の立木祥一郎学芸員と数名の大学教授を除けば、酒造倉庫のオーナーや地元の青年会議所のメンバー、弁護士、企業の経営者など普段は美術と直接関わりのない職業に携わる人々が多く含まれていた。
私も途中から実行委員に加わったのだが、初めてこの委員会のミーティングに出席した時、強く印象に残ったことがある。それは不動産会社を営むメンバーの一人が「このたびは『奈良美智展』で、いろいろとお世話になります。」と私に声をかけてきたことだった。展覧会を主催する側として、彼の口から自然に発せられたのこの言葉を聞くまで、なぜか私は彼がこの展覧会を開催する当事者であるということを実感できずにいた。美術の展覧会というのは美術館や画廊など、いわゆるアート業界に携わる人々が主催するもので、それ以外の人々は、部外者という立場でしかサポートできない、という思いがどこかにあったからだ。展覧会を主催する側としての自覚と責任感に裏打ちされた彼のさりげない一言は、ボランティアに対する私の偏狭な考え方を打ち砕いた。
展覧会の準備段階から終了までの間に、ボランティアのみで運営するがゆえのさまざまな問題が浮上した。会場の管理は誰がするか、作品の監視はどのようにするか、など。だが、こうした困難を乗り越える時、最後によりどころとなったのは、ボランティアめいめいの当事者意識とそれに伴った行動力であったように思う。つまり、自分はこの展覧会を実現する側の立場にあるのだという自覚と、その展覧会を少しでもよいものにするために自らが働きかけるという力だ。結局「奈良美智展弘前」は人口約十八万人の街にして約六万人という驚異的な入場者及びイベント参加者数を記録し、大盛況のうちに幕を閉じるのだが、もしこうした個々のボランティアの当事者意識や行動力がなかったら、この展覧会は成功どころか、実現にも至らなかっただろう。
美術館がボランティアを積極的に取り入れるということは、今では決して珍しいことではない。しかし、これまでのいわゆる〈美術館ボランティア〉の多くは、美術館のお手伝い的な役割に徹するか、ボランティアという形で美術館のサービスを享受するといった、専ら美術館に従属した位置づけをなされてきたようだ。
「奈良美智展弘前」を体験した今、何かもっと違った〈美術館ボランティア〉があるような気がしている。それは必ずしも館の中に、館の活動と直結した形で在るのではなく、館の外に在りながらも館と同列に位置し、同じ方向を目指して歩んでいる、言ってみれば館の友軍のような存在だ。そして学芸員もボランティアもその両組織の間を自由に行き交い、そこでの交流から何かを生み出していく。これから建てられる美術館とボランティアにはそうした関係がふさわしいのではないだろうか。
青森県*ボランティアの大冒険
高田敬子(青森県環境生活部NPO・ボランティア推進監)
青森県内の3つの都市で、市民によるアートプロジェクトが街を元気づけている。昨年夏、3500人ものボランティアによる企画運営で話題を呼んだ「奈良美智展弘前」、八戸市の街を舞台に展開された「ラグタイム展」、そして今青森市では、古民家を会場に「ナンシー関消しゴム版画展」の準備が進められている。こうした市民プロジェクトが活発化してきた背景として様々なことが考えられるが、注目しておきたいのは、3つの都市の間で経験や情報の蓄積・交換、そしてメンバー同士の相互交流があったことである。
市民によるアートプロジェクトの先駆けは3年前に遡る。1999年秋、「トヨタアートマネジメント講座〜青森セッション」が行われたが、これを企画運営したのは、地元の美術家、建築家、NPO、自治体職員、マスコミ関係者、そして学芸員から成るボランティアの実行委員である。これは、アートマネジメントを学ぶ場を創る活動であったが、そのまま実践する者同士の出会いと交流の場となった。「奈良美智展」も「ナンシー関展」も、コアメンバーはここを出発点としている。
この翌年行われた「インタ―ナショナル・アーティスト・イン・レジデンス青森―水辺」は、青森市とNPOとボランティアの協働による企画運営となった。この経験は、現在、国際芸術センターのサポーターや「ナンシー関展」へと引き継がれている。また、この時公演を行った八戸市の劇団「モレキュラーシアター」のメンバーは、市在住アーティストとともにアートボランティア「イカノフ」を立ち上げて、「ラグタイム展」を主催するなど八戸市のアートシーンを盛り上げている。
3年前に投じられた一石は、県内に広がり重なる波紋を巻き起こした。この波紋の底のは何があるのだろうか。色彩と形が溢れるねぶた祭り、三社大祭など、この地域の祭りのマネジメントの歴史は、アートプロジェクトへの関心や関わりを容易にする土壌になっているのかもしれない。
esperanza エスペランサ 青森県立美術館に望む
第5回 河島伸子(同志社大学助教授)
成熟したセクター、その本質的課題
美術館というものは、文化施設の中ではもっとも数も多く、欧米の施設と比較して、少なくとも形式上はそれほど異ならない「成熟した」セクター、と言ってもよいであろう。これに比して、劇場やコンサートホールは、この10年で急激に成長をとげたものの、それ以前は、文化施設としては、驚くほど質の低いものであった。そもそも各地にあった文化会館の類は、多目的ホールとして建設されていたため、どのような種類の公演にとっても中途半端で使いづらいものであった。また運営の専門家が不在で、役所から出向している職員が、特に企画の意図や芸術的判断なしに、単に「パッケージを買って」自主事業公演を時折展開するものの、基本的には貸し館事業であり、発信する文化のない建物でしかなかった。それが、この1990年代を通じ、大きく変化した。第一に演劇なりクラシック音楽に特化した施設が生まれ、建物のつくりとしても高度な専門性を誇るものが生まれた。第二に、マネジメント面においても、芸術面での卓越性を目指すタイプのものや、地域社会とのつながりを重視した活動を展開するところなどが出現してきた。
このように劇的な変化を遂げた文化ホールに比べて、美術館はどうであったろうか。進化を遂げていないという批判的な声もあるようだが、変化が全くなかったとは言えないであろう。例えばこの10年ほどの間に、インタラクティブな展示法、ギャラリー・トーク、美術館ボランティア、アーティスト・イン・レジデンスなどの新しい活動が随分見られるようになった。また館内での活動を美術に限らず、音楽コンサートやパフォーマンス、映画の上映会などを行う美術館も増えてきている。芸術面における多様性と創造性を伸ばす方向と、地域社会・一般の人々へのサービス充実という二つの方向に向けた動きがあったという点、ホールなどと同様の変化を遂げてきたと言える。
しかし本質的課題であるのは、これらの新しい活動が、「とりあえず」のメニューになってしまいがちなことである。すなわち、ボランティア制度やギャラリー・トークもやっています、という形をつくることは、本来は美術と一般の人々との関係を豊かにするための手段であるが、それが目的化しているきらいがある。目的を徹底的に考えないままに形だけ導入しているため、形にも工夫がない場合が大半である。今後生まれる美術館、そして既存の美術館にも、一番期待したいのは、一言で言えば、何か制度をつくることではなく、むしろ何をどのようにしたいのか、徹底的に考えた上でそれに最適な活動を起こしていくことである。以下、具体的には何をしていって欲しいか、三点取り上げる。
第一は、戦略的なマーケティングの考え方を導入することである。マーケティングというと、「営業=モノを売ること」というイメージがあり、美術館のように非営利で芸術を扱う公共の団体にふさわしくない、と考えられがちである。しかし非営利の公共団体であるからこそ、その活動が美術界及び地域社会全体にとって何らかの利益をもたらさなければ、館の存在意義はない。そこでマーケティングの考え方は非常に重要になってくる。ここでいう戦略的マーケティングとは、例えば企画展への入館者数を増やすために派手な広告をうつことを指すのではなく、展覧会とは関係なく美術館を利用する人々なども増やしていき、美術館と人々とのつながりを深めていくことを指す。そのためには、美術館に人々が何を期待しているのか、そこで何を得ているのか、あるいは美術館についてどのようなイメージを持っているのか、などの点につき詳しく調査を行い、美術館との関係において異なるいくつかのグループ特性を理解しなければならない。小さな子どものいる家族はあまり美術館では見かけないとしたら、それはなぜなのか。あるいは美術館を頻繁に利用する人々は、どのようなサービスや企画を求めているのか。要するにそれぞれの顧客の立場にたった自己点検と企画開発が必要なのである。
第二番目には、地域社会からの参加とネットワークを促すような仕組みをつくることである。美術館に学芸員という専門家がいることの意義は大きいのだが、その専門性こそが地域社会とのバリアをつくってしまっているという弊害もある。美術館ボランティアという制度がこれほど普及したのは、暇な人が多い、あるいは単に美術に興味のある人が多いということではなく、「美術に積極的に関わりたい」という思いを持つ人が多いことを示唆する。彼らは何をしたら自分の欲求が満たせるのか、明確な意識を持っているとは限らないが、ボランティア制度の中で決められた単純作業を行ったり創作講座、講演会に出席したりすること以上に、能動的な関わりを模索しつつある。究極的には美術館・展覧会の企画や運営に関わりたい、そこで自らの個性や創造性を発揮したいという気持ちもある。このような人々の存在は美術館スタッフにとっては脅威でもあり、また仕事の負担増につながると見えるかもしれない。しかし、市民やNPOが積極的に関わることにより、常に外部からの情報と新しい空気が入り込み、ともすると内側にこもりがちである美術館が活性化することは間違いない。
第三番目には、「美術館は優れた芸術を市民に紹介する場所である」という施設中心的な考え方を抜け出て、美術館は「芸術と市民の出会いづくりのきっかけを行う触媒的存在」という方向に向かうことである。最近は文化ホールにおいても、お客さんが来るのを待って会場で何か公演を行う形態にとどまらず、ホールが企画した‘出前公演’を学校や病院に届けるという、アウトリーチ活動が始まっている。美術館では、会場の設備や警備面での問題が先に立ち、なかなか‘出前展覧会’はできないと思われがちであろう。しかし、特に現代アートの世界では、作品の形態自体も変化している。今後の美術館は、現代アートにおける思想の進化に合わせ、美術のあり方そのものに挑戦をする、新しい文化施設の役割を模索することこそが必要なのである。
かわしま・のぶこ
同志社大学経済学部・経済研究科助教授、放送大学客員助教授。東京大学教養学部教養学科(国際関係論専攻)卒業後、電通総研研究員、英国ウォーリオック大学文化政策研究センターリサーチフェローを経て、1999年より同志社大学にて、文化政策論及び文化経済を教える。共著に『文化政策学』(有斐閣)、『アーツ・マネージメント』(放送大学教育振興会)、『企業の社会貢献』(日本経済新聞社)、『NPOとは何か』(同)など。ウォーリック大学文化政策研究センター・リサーチアソシエート、文化経済学会〈日本〉理事、日本NPO学会理事、国際文化政策学会学術委員。
学芸員エッセイ
関野凖一郎と今純三 〜銅版画と青森を結ぶ糸〜 (前編)
菅野 晶(学芸員)
版画と聞いて思い浮かべるのは、日本では木版画、西洋では銅版画だといいます。近代の日本における銅版画の歩みは、同じく西洋伝来の油彩画に比べると地味ですが、多くの作家達がこの舶来の技法に取り組み、自分の表現を作り上げることで着実に普及してゆきました。今回はこの銅版画と青森とのこれまであまり知られていない結びつきをご紹介します。
キーパーソンは、関野凖一郎(1914年〜1988年)です。青森を代表する版画家の一人である彼は、木版画だけでなく銅版画や石版画も制作し、実に多彩な活動をしています。ここでは1950年代の前半に、当時東京の杉並区にあった自宅で開催していたという銅版画の研究会に注目します。
関野の著作『版画を築いた人々』の中の「火葬町銅版画研究所」と題された章によると、この研究会は1950〜51年頃、戦後の物不足で画材の入手もままならないなか、月一回程数名が集まってはじまり、やがて「研究生」が増え、会費を取って実技指導をする本格的なものに発展していきました。奇妙な命名は、当時家のそばに火葬場があったことによるようです。文中には研究会を訪れた人物の名もたくさん記されています。なかでも駒井哲郎、浜田知明、浜口陽三は、いずれも1950年代に海外の国際展で高く評価され、日本の美術界にも大きな刺激を与えた作家です。その「ブレイク直前」の彼等が皆、ここに顔を出しているとは興味深いことです。
関野より六歳ほど年下の駒井は当時三十代の初め。二人は戦前から親しい友人で、研究会では共に指導にあたりました。1950年前後から『束の間の幻影』など深い内面性と繊細なマチエールをもつ初期の代表作を制作し、まもなく瀧口修造の「実験工房」にも参加しています。この頃は彼の最も充実した時期の一つといえるでしょう。
当時三十代前半の浜田は、戦時中の従軍体験を表現する方法を模索する中で銅版画に着目し、駒井の紹介でやってきます。駒井や関野からプレス機の制作や技術上の助言を受け、まもなく戦争と人間という主題に鋭い造形感覚で切り込んだ「初年兵哀歌」シリーズを制作して注目を集めます。※1
浜口の訪問は、研究会が始まって間もなくのことのようです。四十歳を過ぎた頃ですでに外遊体験もあった彼は、ここで大きな収穫を得ます。メゾティントという技法では、銅版に特殊な下地を作るためにベルソーという専用の道具が必要ですが、当時日本では入手困難でした。関野はベルソーなしでこの下地を作る方法を実演してみせたといいます。※2実際に、浜口の作品目録には1951年からメゾティントによる作品が登場します。数年後に渡仏して本格的にメゾティントに取り組み、「カラー・メゾティント」という技法を開発して独自の世界を築きます。
他にも、当時十代後半から二十代前半だった加納光於、小林ドンゲ、野中ユリ、吉田穂高など、やがてそれぞれ個性的な活動を展開する作家たちや、明治生まれの川口軌外、関野と同世代の桂ゆきなど、生涯にわたって斬新な表現を模索し続けた画家の名前があります。
意外なところでは、漫画『のらくろ』の作者田河水泡が第一回から参加しています。当時五十代初めの彼は、美術学生だった頃にはマヴォ(MAVO)という前衛美術のグループに加わったこともある多才な人でした。実は関野の師である恩地孝四郎とは隣家に住む親しい友人であり、関野に研究会開催を勧めたのは彼だということです。
研究会では銅版、インクの材料から紙まで自前で調達し、道具を工夫して版を作り、プレス機も自作したり、改良を重ねたりしました。理想的とはとてもいえない環境の中で、銅版画の魅力に惹かれた多彩な人物がここに集い、やがてそれぞれの道を歩んで行ったのです。
それにしても、関野はこのような研究会を主催できる銅版画についての知識と技術をどこで身につけたのでしょうか。そこには弘前出身の今純三の存在がありました。
※2「版画芸術」第111号(阿部出版 2001年3月発行)浜口陽三追悼特集「浜口陽三・人とその作品」(三木哲夫著)にこのエピソードが取り上げられています(P.69)

