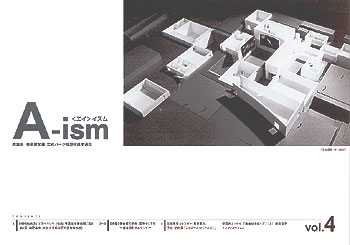
A-ism vol.4
A-ism (エイ・イズム) はAomorism (アオモリズム) 、つまり「青森主義」を意味します。青森特有の精神風土を活かしながら、新世紀にふさわしい個性的な美術館を目指す館の情報を、A-ismにて発信してきました。
※美術館整備通信をvol4より「A-ism」に名称変更。
特集 美術館の思想、着想、そして形−基本設計をめぐって−
平成13年3月、美術館建築の骨格を決める基本設計が完成しました。活動、運営についての本県の美術館の理想は、そこにどのような形で反映されているのか。プランの概要を、背後にある思想やその具象化にあたっての着想とともに紹介し、基本設計生成のプロセスを浮き彫りにします。
まだ見ぬ青森県の美術館
黒岩恭介(青森県美術館整備推進監)
基本設計を矯(た)めつ眇(すが)めつしていると、美術館のダイナミックな構造がイメージされてくる。平面よりも断面系をオリジナル・コンセプトとして主張するこの建築は、これまでにない特質を顕わにしている。それが何であるのかを述べる前に、われわれが、設計にあたって要求したいくつかの点を、まず明らかにしておこう。たとえば作品鑑賞について、選択導線を構想した。つまり鑑賞の順路が一義的に決定されているのではなく、多様な順路を選択可能にするような導線である。また常設展示の重要性を強調する展示室を要求した。もちろんシャガールの大作『アレコ』のための展示空間も要求した。青木案はそのようなわれわれの要求に見事に応えている。
展示室は上下二層に分れて展開しているが、これまでの多くの美術館に見られるように、企画展示室と常設展示室が分断されていない。基本的には下層が企画展示室に当てられているが、中心には『アレコ』の常設展示空間が大きく取られており、その周りを企画展示室が取り囲む配置になっている。そして西北に位置する土の展示室は常設展示空間として使用され、上層の常設各部屋と有機的に連結する構造である。それは、ややもすれば企画展あるいは特別展を目当てに来館する鑑賞者に対して、美術館の命ともいえるパーマネント・コレクションをできる限り眼にする機会を増やしたいという常設重視のコンセプトから来ている。
常設の各室がかなり小さめに区画、配置されていること、また選択導線の導入もまた、常設展示にありがちな単調さを避け、変化に富んだ、展示環境を作りたいというというわれわれの考え方からである。基本的にはワン・ルーム、ワン・アーティストの展示、それが不可能な場合でもできるだけテーマ性を持たせた展示を心がけたいという美術館の方向性を端的に指し示すものである。
さて展示空間に対するこのような配慮は、ひとつには、ホワイト・キューブに対する反省から生まれている。展示空間の中性性をどう克服するかが、この建築の重要な課題だったように思う。今まで美術館の展示室として理想とされたホワイト・キューブは、地塗りを施した白いカンヴァスのような空間として想定された。その空間は、壁掛けであれ、床置きであれ、あらゆる種類のアートを「図」として効果的に浮き立たせる、特性のない「地」としての役割を担っていた。しかし、話はそれだけではすまない。アートに本来備わっている毒気、あるいは問題提起、あるいは時代や社会との関わり、等々を、ホワイト・キューブは、中性化あるいは蒸留してしまう傾向にあるのではないか。それは展示室の問題ではなく、制度としての美術館そのものに関わる問題かもしれないけれど。
さて美術館の中のそのような制度化された空間を、いかに現実世界に開くか、あるいは人々の生活の場としていかに機能させるかという、本当に実現することの困難な、しかしこれからの美術館としてやらなければいけない課題と、青森県の美術館は取り組もうとしているのである。青木淳のこのタタキと版築(はんちく)の展示空間は、建築的なその特殊解と考えてよいだろう。
平成十七年度の開館を目指す青森県の美術館は、県内初めての本格的美術館として登場することになる。これまでいかんともなし難かった青森県の美術愛好家の美術に対する飢餓感を癒すために、種々様々な展覧会をここで開催していき、その期待に応えたいと願っている。これには何の問題もないだろう。
ところで、青森県の美術館は、館内にレジデンス施設を内包しているが、それは日本の美術館としては極めて珍しい試みである。その意味するところは何かというと、あたりまえの話だが、青森の美術館に、現在活動しているアーティストが滞在して、仕事をするということである。滞在アーティストは狭義の美術分野に限らない。様々な芸術分野のアーティストが、ここ青森の風土や隣接する三内丸山遺跡のエネルギーに触発されて、多岐にわたる制作あるいは研究を行なうということを意味する。そのような活動プログラムを定期的に実行するということは、青森県の美術館が、現代の美術文化と強い関わりをもつ活動を展開するということであり、そのことによって、青森の美術文化の土壌に強い刺激を提供し、それを耕し、活性化していこうという態度決定のあらわれなのである。
われわれはそうした創作活動の支援を重視し、積極的に取り組みたい。そして同時に、できうる限りそれを公開し、ものを作る現場に立ち会える機会を多く作りたい。それが鑑賞者の、アートの享受と理解を、より深いものにすると信じるからである。そしてそういう視点から、美術館内の各施設は入念に考え抜かれ、計画的に配置整備されているのが、基本設計から読み取れる。
土の展示室
青木淳(建築家)
2000年2月、私たちの案は、設計競技において最優秀案に選ばれました。以降、私たちは、その案に基づきながら、運営にあたられる方々をはじめ関係する多くの方々と様々な議論を重ね、いま2001年の3月、ようやく基本設計をまとめあげたところです。
設計競技案のもっとも根幹にあるアイデアは、その断面構成に現われています。土が上向きに凸凹した地形をつくっています。その上から下向きに凸凹の構造体が覆い被さっています。構造体のある部分は、土にまで達し、またある部分は土に達する手前で終わっています。こういうことの結果、土の凸凹と構造体の凸凹との間に、隙間の空間が生まれています。私たちは、その隙間を展示室として使うことを提案しました。床は土です。壁も場所によってはまた土になるかもしれません。私たちは、そこを「土の展示室」と呼ぶことにしました。展示室は、構造体のなかにも設けられます。そこは「ホワイトキューブの展示室」です。「土の展示室」と「ホワイトキューブの展示室」。こうして、その対極的な二種類の展示室が、交互に現われる。それが設計競技案の建築的な面での、もっとも大切な提案でした。
なぜ「土の展示室」を提案したのかと言えば、この美術館に隣接して三内丸山縄文遺跡があるからでした。というと、話が逆、なのかもしれません。正確に言えば、まずそこに三内丸山縄文遺跡があったのです。この遺跡は非常に重要な意味を持っていました。それは、縄文時代に農耕や栽培が行なわれていたことを証拠だて、それらの起源を弥生時代とする定説をみごとに覆したのです。また、三内丸山では栗や稗が栽培されていたことがわかっています。つまり縄文時代の人々は多品種の栽培と、海や山での狩猟など、自然の生態系と共存しながら生きる術(すべ)を知っていたのでした。縄文時代の農耕は、弥生時代の稲という一品種に片寄った農耕とは異なるものでした。しかし、それは自然との共存という観点からすれば、むしろ弥生時代の農耕よりも優れていると言ってもいい、という意見もあるくらいです。青森の人々にとって、そういう三内丸山縄文遺跡が精神的なシンボルになったことは、想像に難くありませんでした。実際、この遺跡があったからこそ、そこに隣接する総合運動公園を文化の森として再整備することが決定されたのだと私たちは思っています。
そうであれば、その文化の森の中心施設であるこの美術館は、三内丸山縄文遺跡と強い連関をもつべきでしょう。では、どうやって?縄文はあまりに遠い時代です。そのころの建築様式はおろか、彼らが持っていたものの考え方も推測の域を出ません。彼らの思考様式がわからなければ、遺構からその時代の建築様式を正確に演繹(えんえき)することもできません。だとすれば、私たちが推測している縄文様式の建築というのが、本当に縄文時代の様式であったかどうかがわからないのです。私たちは、そんな悩みを抱えながら、三内丸山縄文遺跡に訪れることにしました。私たちがそこで見たものは、類まれな力強さをもった発掘された六本の巨大な柱の根元であり、土を縦横に切ってできたトレンチ(溝)の断面が示す深い時代の積み重なりでした。それらの風景に私たちは圧倒されていました。そしてそのときに、縄文時代そのものを引き継ぐことはできないにしても、その発掘現場の質なら美術館に引き取ることができるのではないか、という着想が私たちのなかに生まれました。美術館の空間を、発掘現場のトレンチ同様に、縦横に走る土の溝でつくりだしました。それが、上向きに凸凹な土の断面だったのです。
もちろん、この美術館は「縄文美術館」ではありません。現代の美術も扱う「県立美術館」です。だから、この「土の展示室」がなぜ美術館空間として相応しいのかという、美術館としての観点も欠かすことができません。あるいは、むしろそちらの方がより重大な問題なのかもしれません。
大谷石(おおやいし)の採掘場がそのまま展示空間として使われたことがあります。パリのクリュニー美術館では、ローマ時代の遺跡をそのかたちで残しながら、展示空間として使われています。これらの展示空間は、スケールとプロポーションと光の状態にまで還元された部屋、つまり「ホワイトキューブ」とは対極的な質を持っています。まずそこには空間としての強い特性があります。またその特性は誰かの作為ではなく、なんらかの正当な根拠があって、それを徹底的に展開した結果としての空間が出現してしまっています。そこにはそこでどう感じて欲しいという意図がないのと同時に、しかし強い質が存在しています。
美術館とは、人間がなにかをつくることに捧げられた空間だと思います。そして、なにかをつくるとき、そのつくる内容を空間が先回りしてしまっていては、ひどい窮屈を感じるものだと考えています。空間は、確かにつくることに先行して存在する場合もあるけれど、そこから読み取る内容はつくる側の手になければならない。つくる人が、その空間を前提として、そこでなにを行なうかを決め、それを実行する。それは、サイトスペシフィックなつくり方と呼ばれるものですが、それができるためには、その空間がある強い質を持っていながら、その質の向こうにこちらのつくることを決めつけるような意図があってはならないと私たちは考えました。
私たち設計者は、つねにそこでどんなことが行なわれるだろうか、という想定なしには空間をつくることはできませんし、またそうすべきではありません。しかし、そうすることが、結果として、そこでのつくることの自由を奪ってもいけない。「土の展示室」は、空間が作品に先行する、つまりサイトスペシフィックな作品に対応する展示室として考えました。土は空間に非常に強い個性を与えます。しかし、その個性は、そこで行なわれることの想定から生まれたものではありません。青森の、この場所だからこそ、生まれてくる空間なのです。
esperanza エスペランサ 青森県立美術館に望む
第1回 西野嘉章(東京大学総合研究博物館教授)
誇りとしての「独善」
待望の施設がいまわれわれの前に姿を現わそうとしている。新しい美術館の誕生は青森県民にとって大きな福音となる。とくに地方分権の流れのなかで地域文化の活性化が求められる時代ゆえ、なおさらである。県の芸術文化活動の実質的な受け皿として、また県民の社会生活の象徴的なランドスケープとして、様々な可能性を秘めたこの巨大施設が、地域の文化拠点として順調に船出できるかどうかは、そのプロセスを支援し、看守する県民の姿勢にかかっている。美術館が存在感を発揮するために必要とする、こう言って良ければ「個性的」な振る舞いを、県民はどこまで許容できるか。芸術文化に接する県民一人一人の理解力の幅と、寛容さの度合いがいま問われているのである。
国内のミュージアムの現状を顧みると、新しい美術館を取り巻く外的な条件は決して甘くない。われわれはいまや美術館・博物館がすでに三千館近くを数えるミュージアム乱立時代にある。しかも、現在構想が固まりつつある新美術館は県立レヴェルの施設として国内最後発であり、かてて加えて、他府県で既存の公立美術館が改修や新修を迎えようとする時期に新しく誕生しようとしている。収蔵品について言えば、平成四年に美術資料取得等基金を設け潤沢な資金を備えてはいるものの、展示品の中核をなす固有のコレクションを蔵していたわけでなく、今後も外部からの作品購入に頼らざるを得ない状況にある。社会教育や情報発信のサーヴィスについてもまた、アーティスト・イン・レジデンス、ハンズオン、デジタル・アーカイヴなど、他所ではすでに「次世代型」事業のあり方が模作されつつある時代に、大型の新しい美術館として発足することになる。
なるほど、こうしてみると青森県の美術館の先行きは容易でなさそうである。しかし、新しい美術館を取り巻く前件を、ネガティヴなものとばかり見る必要はない。最後発の県立美術館というのは立派な属性であって、既存館の持ち合わせぬその特殊性を生かす術(すべ)はないものか。というよりも、そのことをむしろ逆手に取って、国内各地の美術館が経験してきたことを教訓として学び、それらの反省を踏まえつつ新しい事業を興すことができるという点で、青森県の美術館はいまや最良のスタート・ポイントに立っていると考えるべきである。
最後発館の振る舞いとして是非とも避けて欲しいのは、既存の美術館の現状を是認(ぜにん)し、その運営方法を盲従することである。既存館の経験から、これまでなされずにきたことを知悉(ちしつ)し、それを実現するにはどのような手立てが考えられるか、いまいちど冷静に考え直すに若くはない。美術館運営の「常道」なるものを排し、美術館としての独自性を主張するために、組織や運営の面で出来るだけ斬新な仕掛けを工夫すること。当然のことながら、個性の強化のためには、建物や施設のディテールに至るまで、細かく神経を砕かねばならない。これについては幸い、オープンコンペにより青木淳氏という思考において柔軟な建築家を得て、独創的なコンセプトが具体化しつつある。学芸担当者は建築家に対し、機能の充足というミニマムな要求を突きつけるだけでなく、建築空間の構成から設備備品の詳細に至るまで、他では到底実現し得ぬような独創的な装いの実現を求め続けて欲しいと思う。
同様に、活動プログラムや収集事業にも斬新な試みへの挑戦が期待される。いまさら繰り返すまでもないことかもしれないが、実現可能なこととして新美術館に期待する事業を以下に掲げておきたい。
その一つは、「美術館建設基本計画」も触れているが、青森県内の既存の博物館施設および博物館相当施設のネットワーク化の推進である。独りアート情報や単発型イヴェントのやり取りだけでなく、中長期的なスパンでもって人的資源や収蔵品の交流を図り、県内に蓄積された文化的社会資本の高度活用を目指して欲しい。そのためには、社会教育ネットワーク事業、県有美術文化財グローバル・データベース事業、美術品・資料等交流ネットワーク事業など、各種交流・蓄積事業の推進母体としての自覚を強め、ローカルなサテライト(衛星館)を束ねる基幹センターとしてこれまで以上に強いイニシアティヴを発揮する必要がある。この種の事業を推進するにあたっては、公立や私立など各館の設置形態、運営形態の違いがネックになるケースもあるが、粘り強い交渉を通して包括的なネットワークの実現を望む。ミュージアムあるいはそれに類する施設は、公私を問わず県民益、あるいは公益のために存立している。時にその原則を再確認しつつ、積極的に事業推進することが大切である。
高度情報化時代のネットワーク化事業には、当然、海外の美術館との提携も射程に入れなくてはならない。展示の目玉となるシャガールの『アレコ』はそうしたさいに有力な武器の一つとなるであろうし、また長期貸し出しプログラムなどによる展示品の交流展示を実現することもできなくはない。国内外を問わず同規模のミュージアムとの人的・物的提携の推進は、最後発館の事業を軌道に乗せるための数少ない戦略的選択肢なのではないか。
また、コレクション収集については、その対象を郷土ゆかりの作家作品、県外作家の近・現代作品、海外作家の作品を三本柱とする方針のようであるが、作品の購入を主体とする収集事業には自ずと限界があり、また「コンテンポラリー・アート」という価値評価の容易でないものについては対象を絞り込むことの難しさもある。コレクション形成という厄介な問題について現在考え得る最良の方法は、平成十年に文化庁が纏(まと)めた「登録美術品制度」の活用である。いまだ充分に周知されているとは言い難いが、この制度を是非とも積極的に活用して欲しい。寄付行為に対する課税控除が一定限度まで認められることになり、委託、寄託、寄贈の推進が美術館にとって重要課題となりつつある。コレクションの特化方針と相容れない部分もあるが、収蔵事業においてはできるだけ門戸を広げる方向を今後も維持、検討して欲しい。
なにごとにつけ「グローバル化」が叫ばれる時代の風潮のなかにあって、美術館関係者は他館の動向を気にしながら自館の事業の運営を行うのが習い癖になっている。しかし、結果は惨憺(さんたん)たるものである。どこの美術館も他所と似たような事業を繰り返して恥じることがないからである。思えば、欧米で主導的な地位を築いた美術館はどこも、場合によると独善的とも映るほど個性的な事業運営を行っており、むしろそれを誇りにさえしている。作品の収集にしても各種企画の推進にしても、他館に追随せず、自館の独自性を徹底的に追究すること。県立美術館は独善的と詰(なじ)られることを決して懼(おそ)れてはならない。独自の主体的・意志的運営を実現できてこそ、数多ある美術館のなかに埋没することなく、その存在意義を世に謳(うた)うことができるのではないだろうか。美術館の事業は芸術文化に関わる。芸術文化の価値は平準化や画一化を志向する常識的発想からの逸脱や乖離(かいり)の程度によって計られるものであり、時にその「独善」を詰られることに懼(おそ)れをなしてはならないのである。
にしの・よしあき
1952年生まれ。1983年東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。弘前大学人文学部助教授を経て、現在東京大学総合研究博物館教授。博物館工学・美術史学専攻、文学博士。著書に『十五世紀プロヴァンス絵画研究』(1994年、岩波書店)、『博物館学』(1995年、東京大学出版会)、『大学博物館』(1996年、東京大学出版会)、『二十一世紀博物館』(2000年、東京大学出版会)、『装釘考』(2000年、玄風舎)などがある。

